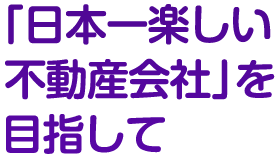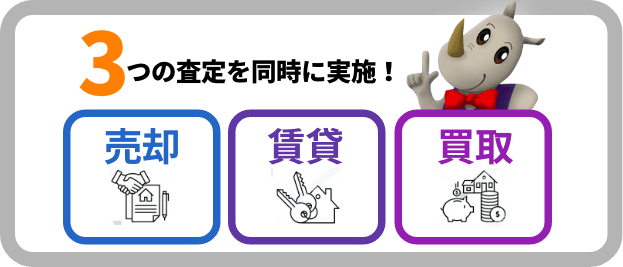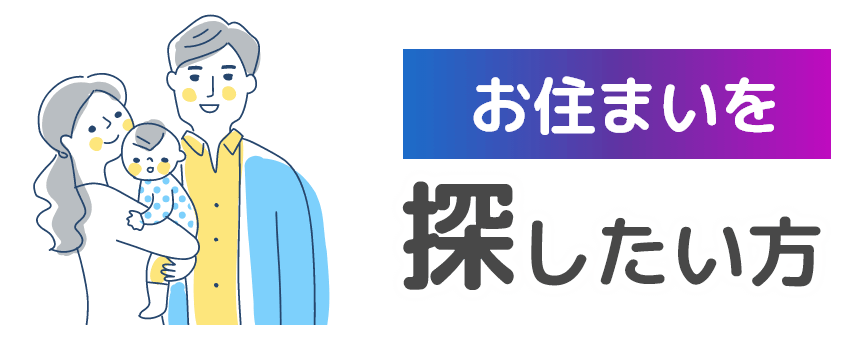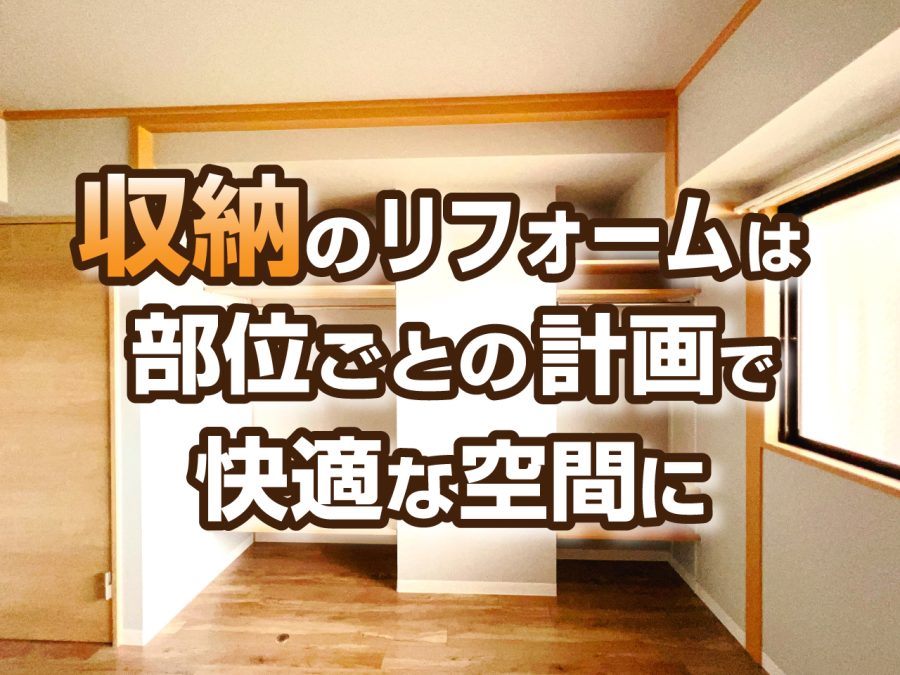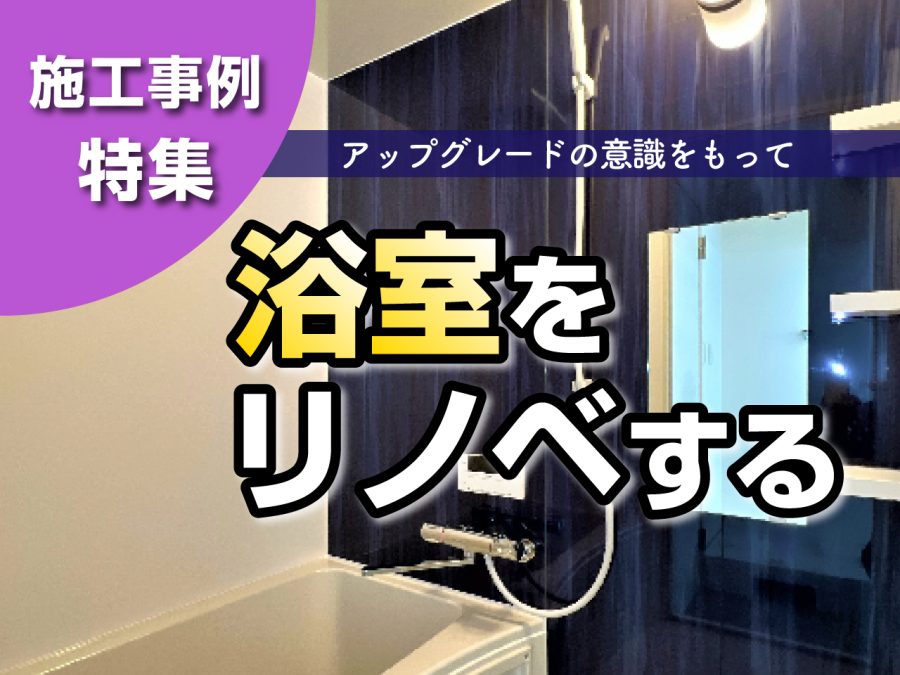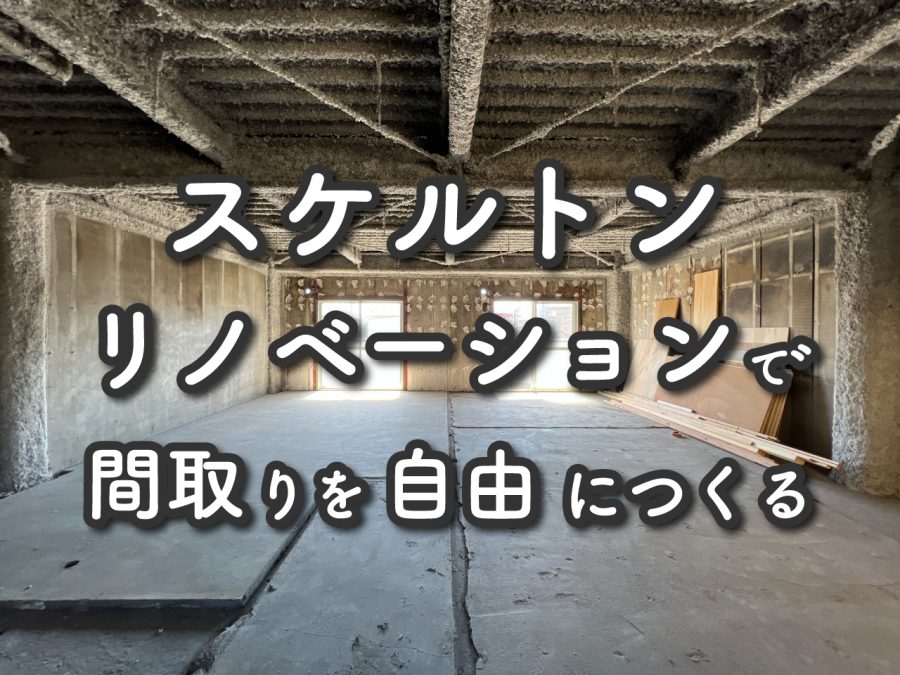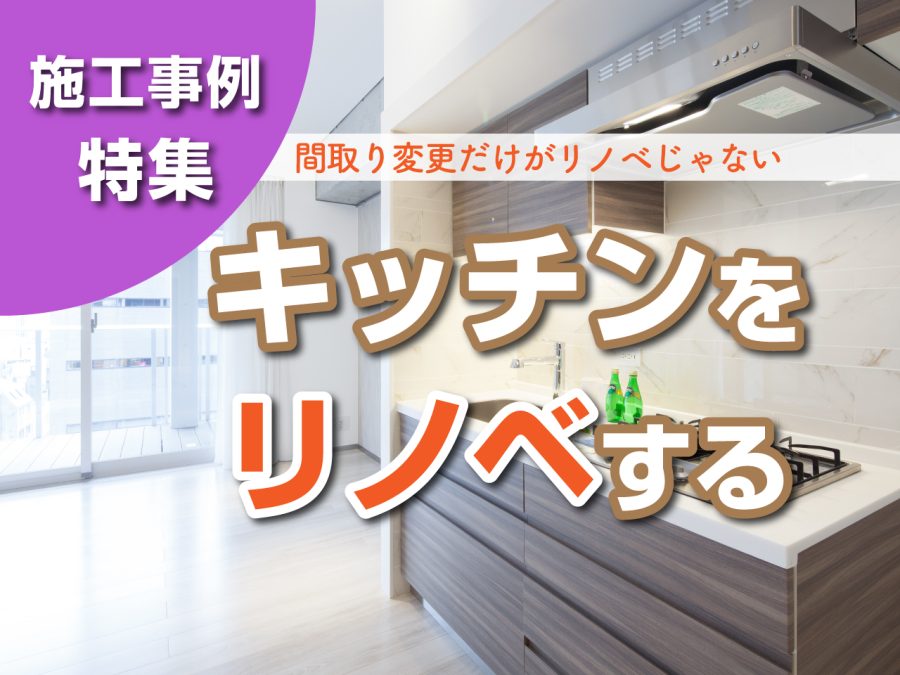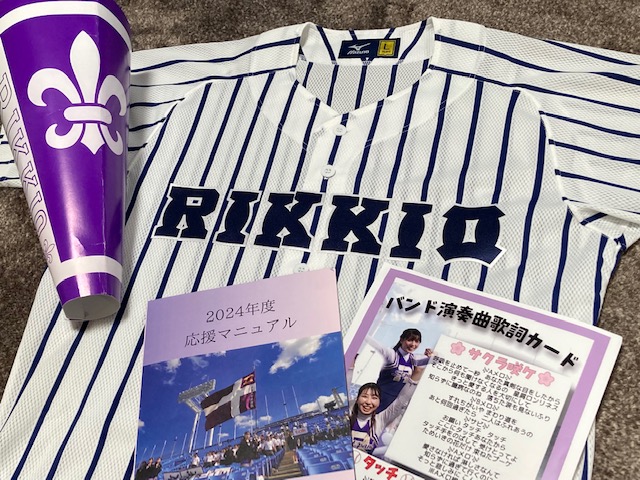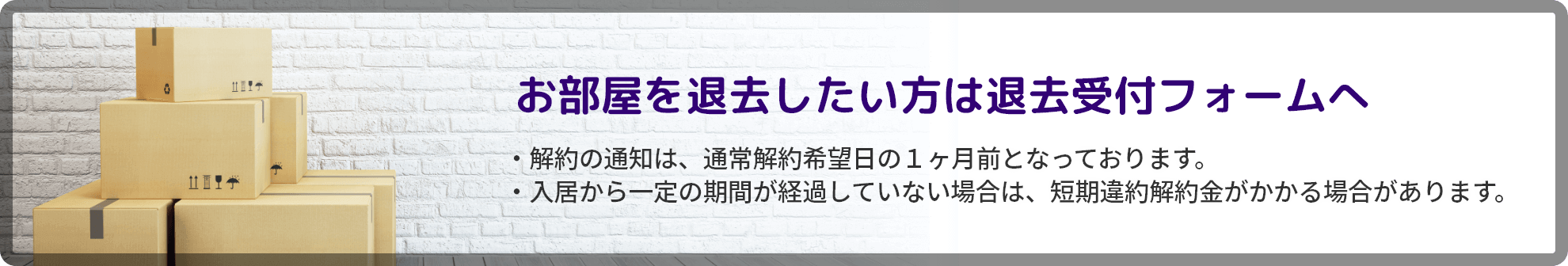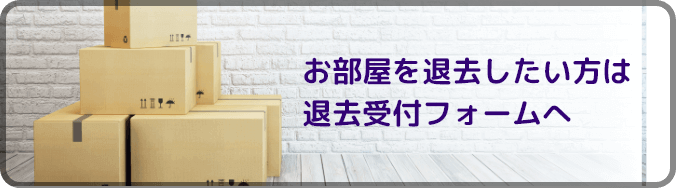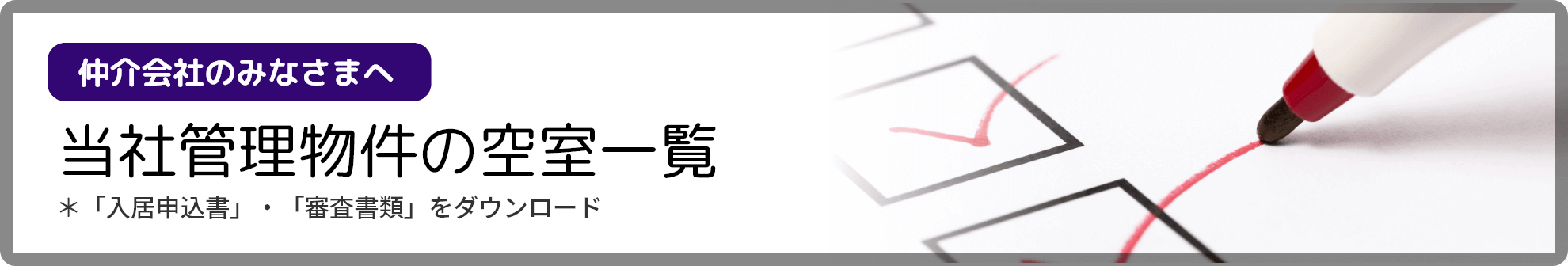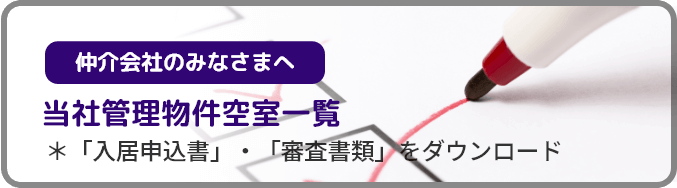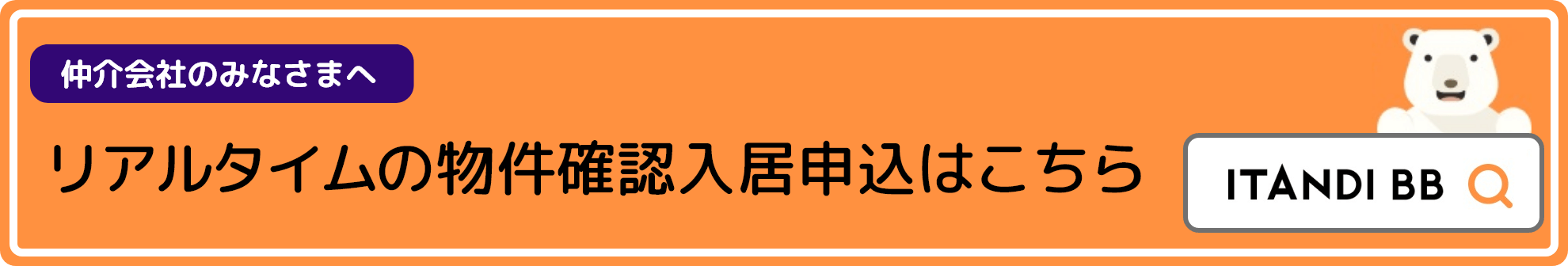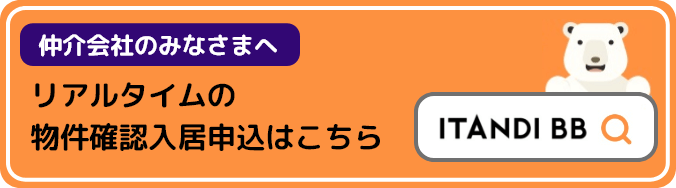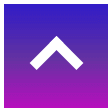清須市・あま市周辺の
「不動産管理・売買・
賃貸・リフォーム」
のことなら
まかせなサイ!

まかせなサイ

私たちが仕事を「楽しい」と思うことで、
お客さまも私たちのサービスを「楽しい」と
感じていただけると信じています。社員もお客様も楽しい、
「日本一楽しい不動産会社」を目指しています。
- セミナー
- 2024.03.25
- 第10回オーナーセミナー開催決定
- お知らせ
- 2023.12.15
- < 年末年始休業日のお知らせ > 令和5年12月28日(木)~令和6年1月3日(水)までお休みさせていただきます。
- TOPIC
- 2023.10.27
- 育児休業取得スタッフの体験レポート
- セミナー
- 2023.09.18
- 第9回オーナーセミナー開催決定
みんなで助け合う
チームワーク
あふれる環境づくりを
地域の暮らしのニーズに応え、ウィズコーポレーションのサービスが「やっぱり、いいね」と言っていただけるようになることが、私たちの目指す未来です。お部屋探しやマイホームの購入、不動産の活用や就職など、人生の様々なシーンでサービスを提供しています。
そこでの主役となるのは、当社で活躍する社員です。新規の事業も立ち上げ、若い力と中堅の行動力、熟練の総合力のいずれも活躍するフィールドが広がっています。さらに活躍が求められる今だからこそ、新しいエネルギーを持った方にぜひ、チャレンジして頂きたいと思っております。皆さんとともに新たな未来へ歩むことを楽しみにしております。

Copyright © WIZ CORPORATION
Co., Ltd. All Rights Reserved.